目次
子どもの国語力を伸ばしたい
その方法は皆さんがお分かりの通り「読書」ですが、そんな話をする為にわざわざ記事は書きません。
令和的新事実、国語力を延ばすのは
ジェスチャーコミュニケーションです。
え?何となく意味は分かりますが、どうするのか?
説明しますね。
その前にこの問題を解いてもらいたいと思います。
国語力テスト
例文:
ニックネームとは通称とか愛称という意味があります。
例えば「よっちゃん」は男女に関係なく使う事があるニックネームです。
男の子の「よしお」さんにも使うし女の子の「よしえ」さんにも使います。
私も「よしこ」ですが、そう呼ばれてました。
問:よしこさんのニックネームは何ですか?
・・・・
分かりますね
「よっちゃん」です。
そんな当たり前の事ですが
読解力の低下した現代の小中学生においてこのような問題を解けるのが中学生が5割。
小学校高学年で3割。
試しにお子さんに解かせてください。
「通称?」
「愛称?」
「そう?」
などと答える事があります。
文科省も国語力の低下は懸念しており、力を入れていきたい。
しかし、活字離れが加速した現代で手をこまねいているのが現状です。
本来、国語力というのは簡潔明瞭に言語や文をまとめる事です。
しかし、それは「量」を創作出来る事が前提の条件となっています。
量と質、作文の書き方は以下に詳しく書いています。
ジェスチャーコミュニケーション
ジェスチャーコミュニケーションとは平たく言えば
「大げさにリアクションを取る」
ものです。
恐らく、小学校に上がる前までは比較的、実施している人が多いと思います。
初めて立った、話した、お絵かきした。その時に手を叩きながら「すごーーい」と褒めたでしょう。
脳は褒められるのが大好きです、同時にどう褒めるかで前頭葉や側頭葉の発達も変わってきます。
小学生になっても、しっかりと(大げさに)褒めましょう。
もし、人目が気になるのならハイタッチでも構いません。
表情で気持ちを込めながら行うのです。
それを子どもが小さい時だけでなく、小学校高学年になっても継続するのです。
子どもがテストで良い点を取ったといえば「いえーーい、やったね。いつも頑張ってたもんね」と声掛けしながらガッツポーズを取ります。
悲しい事があれば、悲しむ表情をしながら会話をします。
「自分が思っているより少し大げさに」がコツです。
通常のコミュニケーションに加えジェスチャーコミュニケーションでは、言語だけでなくジェスチャーや表情を見ながら、より複雑な情報処理をします。
その複雑な情報処理が脳の活性化を図るのです。

PublicDomainPictures / Pixabay
子どもの国語力アップに読み聞かせは何歳まで有効か
小さい頃、読み聞かせをしている家庭とそうでない家庭の国語力、すなわち(言語の)情報処理能力に差が出てくる事は周知の事実ですよね。
もし、あなたの子どもがまだ、未就学児なら積極的に読み聞かせをしましょう。
コツとしては、目を見ながら表情豊かに行います。
その工夫をするかしないかでは大きな差がついてきます・・
ちょっと待ってください。
読み聞かせの対象年齢はもっと長く小学校の間は有効な事が分かっています。
例えば、世界学習到達度テストにおいて国語力トップのフィンランド。
フィンランドでは小学校の子に対し読み聞かせをする文化があるそうです。
このように読み聞かせ、すなわち親子の関わる時間が大きく学力に影響を与えます。
国語力の基礎は家庭にある
読み聞かせもそうですが、同じように効果があるのが親子の会話です。
親子の会話の中にこそ、国語力アップのカギがあります。
子どもの「何で」攻撃に出来るだけ付き合い、答えきれなくなったら
「後で一緒に調べよう」など好奇心を摘まない努力が必要です。
会話を増やせと言っても、多くの人が
「会話してるよ」とか「会話を増やすって?」と言います。
そうですよね、急に「話しましょう」では困りますよね。
その親子の会話において最も有効なの手段が次にあります。
「料理のお手伝い」で学力アップ
料理は複雑な工程に加え、先を読む力が問われますよね。
これを火にかけている間にこれを切って、鍋に入れる順番はこうでーっといった具合に。
この先読みの力が前頭葉や頭頂葉が賦活かされます。
これは認知症予防にも推奨されている重要なメソッドです。
更に料理では、調味料の分量について、mlや温度など単位が出てくる事も多いですね。
自然に単位の感覚が身に付き算数的処理能力も上がります。
食材をカットする事で物体を立体的に捉える事が出来るのも重要なメリットです。
算数が得意な子の特徴は数を「量でイメージ出来る」なのです。
50や300という数字を平面的でなく立体的にイメージ出来るかどうかという事です。

djedj / Pixabay
国語力が低下している原因
先ず、国語力の低下には親子、祖父母、友人などのリアルコミュニケーションの希薄さが原因となっている事が分かってきました。
例えば20年前の子と比べると、line、TwitterなどのSNSでのコミュニケーションは増えましたよね。
あれは遠く離れた人や、すぐに繋がりたい時に非常に便利です。
しかし、その功罪というべきものにコミュニケーション力の低下。
それを元に国語力の低下があるのです。
言いにくい事でもlineだと言えるのはメリットに思えますが失われた物も多いのです。
例えば、昔の学生は恋人に電話する時にスマホが無いので相手の自宅に電話しますよね。
最初からラスボス登場で「親」が出てきます。
そこを交わす為に、電話の向こう側なのに姿勢を正して電話したりしましたよね。
言葉を準備して、相手が話す返答をその場で処理し、より適切な言語を選択していく。
SNSと違いレスポンス(反応速度)が求められます。
S(主語)V(動詞)O(目的)を組み立てて伝える必要があります。
恋愛だけでなく、祖父母や両親との会話や関係の希薄さも国語力低下の要因の1つなのです。
国語力が分かる質問(大人版)
最後にあなたの国語力が高いがどうかの質問します。
中学生以上なら大人として考えていいかもしれません。
いきます。
問題:
「1年の内、30日以上ある月はいくつありますか?」
・・・・・
正解はもちろん
「11」ですよね。
2月を除く11ですね。
これは解けるか否かではありません。
もちろん、解けるのが前提ですが解くまでの時間。
どれだけ要したかが問題なのです。
国語力が高い人は5秒かかりません。
この時に問題をどう捉えるかが国語力です。
30日以上の月を考えてはいけません。
国語力の高い人は30日に満たない月を考えるのです。
言葉の本質を捉え質問の意図を正確に理解するのが国語力です。
ある有名なコメンテーターの格言で私が好きな言葉があります。
(意見を求められたときに)
「何を話すのではなく、何を話さないか」
を考えている。
深い言葉だと感銘を受けています。
まとめ
国語力アップの記事ですが、算数の話も出てきました。
そうです、国語力の高いあなたが理解している通りで国語力は全ての学問の土台です。
特に小中学生においては、問題を解けない理由の9割は問題の意味を理解していない。
それだけです。
宿題を見ている親なら経験していますよね?
間違った問題を親がかみ砕いて質問すると答えが分かるという事が多いのです。
キーワード:子ども 学力 読解力 低い 上げ方 学力向上
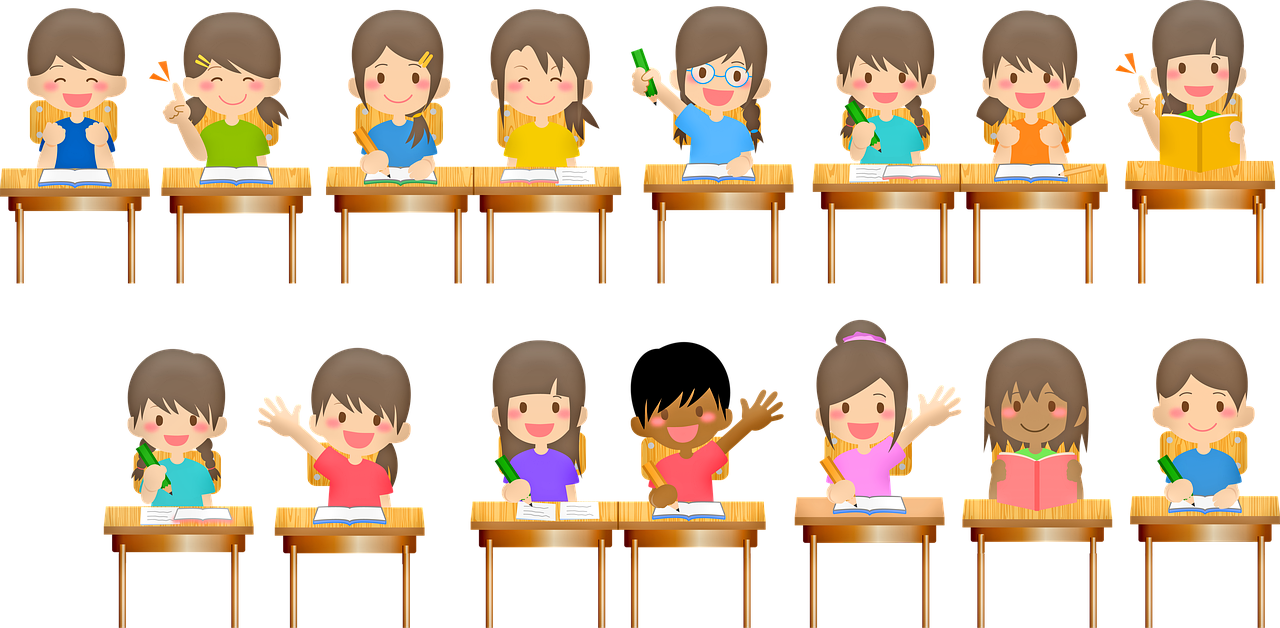

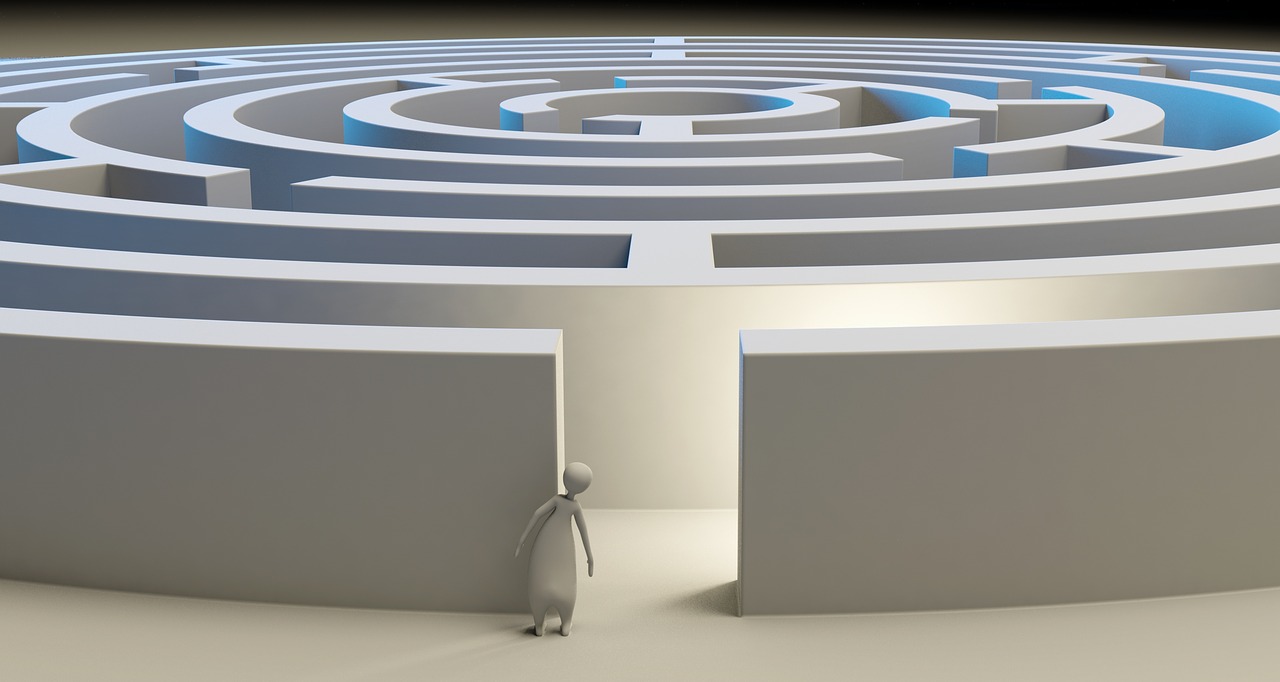
コメントを残す