目次
子どもの便秘対策。赤ちゃんは綿棒浣腸でスッキリ
乳幼児はミルクや母乳などで違いがあるものの、おおよそ、日に3回は排便があるでしょう。多い子だと授乳の度に出る事もあると思います。
そうなると、半日でも、排便が無いと便秘ということになりますね。便秘になると意思を表出出来る子は腹痛を訴えますが乳幼児のサインとしては以下になります。
・発熱する
・機嫌が悪くなる
・ミルクや母乳の飲む量が減る
・(長期的になると)体重が増えなくなる
準備するもの
・綿棒(大人用)
・ベビーオイルかワセリン
・オムツや新聞紙
綿棒浣腸とは
綿棒浣腸とは、その名の通り綿棒で肛門を刺激するのです。注意点としては、赤ちゃん用の細い綿棒は使いません。大人用で構いません。
肛門が裂けたりはしないので安心してください。
仰向けに寝かせて、足を持ち上げます。
出来れば膝をお腹に近づけるように持ちます。
そうすることで、お腹に力を入れやすくなりますよね。
綿棒にベビーオイルやワセリンをしみ込ませて滑りをよくしましょう。
綿棒の綿部分が隠れるほど入れて、ゆっくりと回します。
イメージ的には背中方向です。
この時、刺激ですぐに排便が始まる事も少なくないので、オムツや新聞紙などで受け止める準備もしておきましょう。

andreas160578 / Pixabay
「の」の字マッサージも大切です
綿棒浣腸の前後で出来ると良いです。
赤ちゃんのへそをスタート地点にして、平仮名の「の」を書くように指で押します。
人差し指と中指で強さとしては指が少し沈む程度です(コツは段々と慣れます)。
この時、子どもと目を合わせて話しかけながらやるといいですね。
親と目が合うだけで精神的にリラックスします。
その事で副交感神経が優位に働き腸の動きも活発になります。
やはり子どもが親に触れられる事で一番愛情を感じますので「の」の字マッサージは
便秘解消と情緒の安定で一石二鳥(腸)です
(うまくないか)
排便のメカニズムを知ろう
ウンチはどうやって出てくるのか。簡単に説明していきましょう。
先ず、前日~数時間前に食べた食物は胃→小腸→大腸に行きます。
大腸は上に上がる上行結腸→左から右に流れる横行結腸→下に降りる下行結腸と移動し肛門に近いS字結腸、直腸、そして排出されます。
大腸の上にあがる、右に流れる、下におりるというステージの流れが平仮名の「の」に近いので「の」の字マッサージがあるんですね。
脳と筋肉の巧みな連携でうんちは出てくる
食事をするとトイレに行きたくなりますか?それは正常です。
胃に食物が入ると大腸の動きが活発になります(新しいの来たから早く出て行けよ)
そしてS字結腸あたりに溜まると、脳が検知して、肛門括約筋という筋肉を緩めるよう指示を出します。
その指示のタイミングと我々がお腹に力を入れるタイミングが合えばうんちは排出されるのです。
例えば脳卒中になると高い確率で便秘になります。
それは脳からの指令と筋肉の動きがうまく行かなくなるのも大きな原因の一つです。

AnnaliseArt / Pixabay
ウンチの回数を年齢別にみてみよう。
| 0~3ヵ月(母乳>ミルク) | 3回/日 20回/週 |
| 0~3ヵ月(母乳<ミルク) | 2回/日 15回/週 |
| 4か月~12か月 | 1.8回/日 13回/週 |
| 1歳~3歳 | 1.5回/日 10回/週 |
| 4歳~大人 | 1回/日 7回/週 |
この回数が出ないから、ただちに便秘、異常ではないですが、大まかな目安にはなるでしょう。
現代人に便秘が多い原因
食事や運動不足は大きな原因ですが、それより大きな影響をもたらしているのは「洋式トイレの普及」です。洋式トイレは非常に便利ですよね。
普及したことで高齢者も安全に用を足せるし、トイレ内の転倒も激減しました。
その一方で功罪と言われる1つが便秘です。直腸肛門角といって、洋式トイレでは排便がしにくい体制なのです。
特に子どもは洋式トイレに座ると足も届いていないですよね(見た目はかわいいですけど)
足置き台を使おう
足が届かずにお腹に力が入りにくい、肛門と直腸の角度が不適切な対処方は足置き台です。
子どもが便秘の時は特に使えます。
足置き台を用意して少しでも和式トイレの姿勢に近づける。それだけで排便は容易になります。
※高齢者にも有効です。
食後はトイレに座る習慣をつけよう同じ時間にトイレに行こう。
子どもはこれが意外に大事で効果的です。お子さんがいる方は経験あるかも。子どもが
子「お腹痛い」
親「トイレに行きなさい」
子「(どうせ)出ない」
親「いいから座ってきなさい」
子「うんこ出たよ」
親「ほらー」
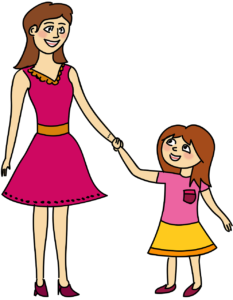
MiluCernochova / Pixabay
これ、経験ないですか?
子どもは便意を適切に処理していない事がありますよね。
よって、食後はトイレに座ってみるというのをトイレトレーニングの頃からやっておくと、小学生になっても排便習慣がつきやすいです。
便秘習慣に陥ると大人になっても続きます。
3食必ず取ろう
これも大切ですね。
排便のメカニズムに書きましたが食べると腸が動くのは「胃-大腸反射」といって医学的にも重要な反射です。
少量でも食事は取る必要はあります。水分も大事ですので、起きたら常温の水を少し飲むだけでも便秘解消の手助けになります。
便秘と睡眠の関係
これも大きな関係がありますよね。交感神経とか副交感神経とか聞いた事ありますか?いわゆる自律神経ですね。
交感神経と副交感神経のバランスが取れることが重要ですが、副交感神経の働きの一つに
腸の蠕動運動(ミミズが動く時のような)の促進があります。
睡眠時は副交感神経ですので、睡眠不足だと腸の動きが不十分で便秘になるのは想像がつきますね。

smengelsrud / Pixabay
(余談)お腹がグーとなる。あれは腸の蠕動運動の音です。
シーンとした会議や授業中にお腹が鳴って恥ずかしい思いをした人はいますか?
あれは腸の蠕動運動です。
恐らくあなたリラックスしていたのでしょう。
体には良い事ですが仕事や授業中は交感神経を優位に働かせましょう(笑)。
スポーツをしている時や集中している時にお腹が鳴ったり空いたりすることはありませんよね。
それが終わったとたんにそうなる事はありますが。それはあなたが交感神経優位に頑張っていたからです。
キーワード:子ども 吐き気 お腹いたい 食欲ない トイレ


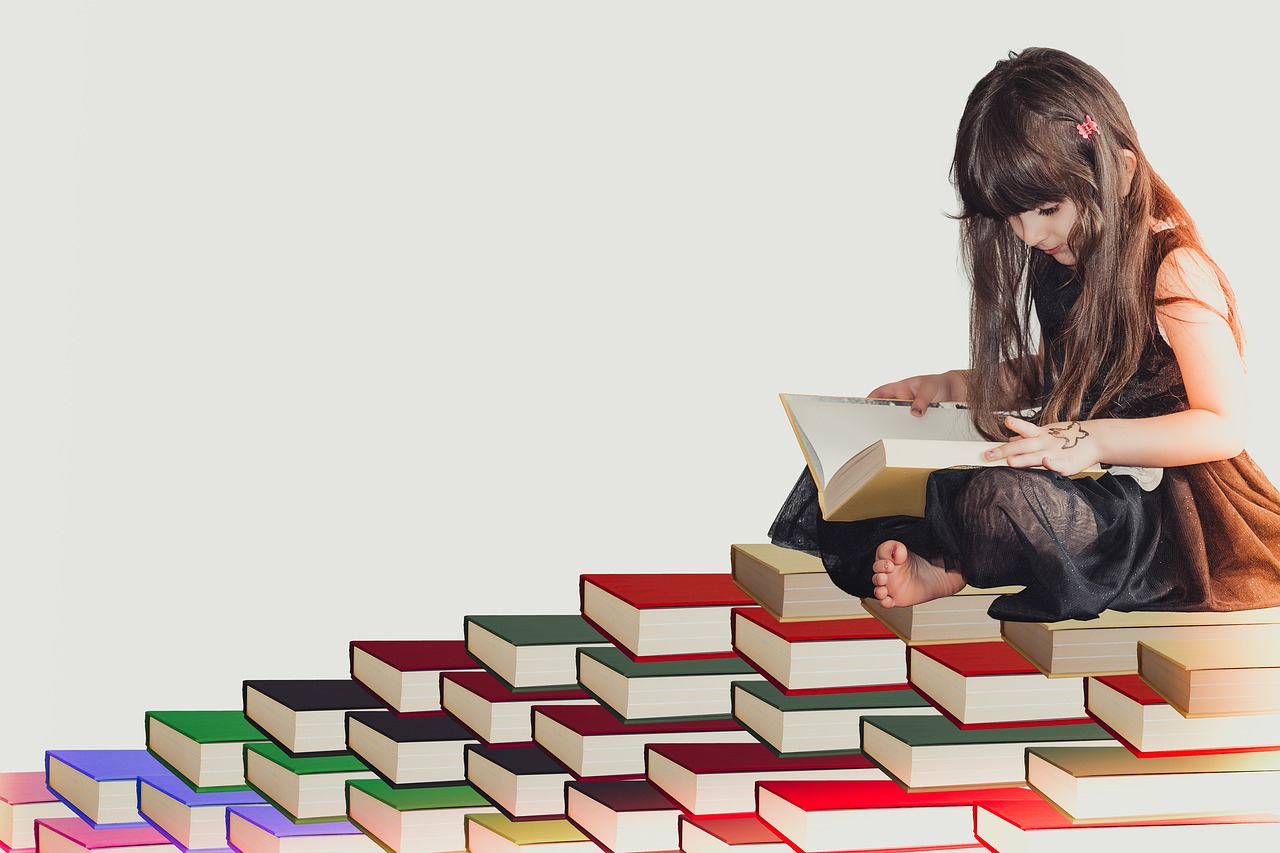
コメントを残す